第2回合宿(SDN/クラウドミニプログラムコンテスト2017)
- labs-admin
- 2017年9月15日
- 読了時間: 3分

第1回合宿後、各チームは設定テーマに基づき、週1回程度のメンターとの進捗確認を行いながら、開発に望みました。 今回は、その成果を披露するミニプログラムコンテスト(以下、ミニプロコン)のほか、協賛企業セッション、チームミーティング、プレゼンテーション講座と、盛りだくさんの予定を精力的にこなしました。
ミニプロコンは、参加者たちが自ら設定したテーマに沿ってここまで行ってきた、企画、調査、開発の成果を中間発表する、本プログラムの重要なマイルストーンの1つです。ここで得られるメンター陣などからの質問やコメントは、参加者にとって、立ちはだかる壁を突破する手がかりや、テーマを深化させる大きなヒントになります。 発表での各チームの持ち時間は30分とし、そのなかで、プレゼン、デモ、質疑応答を行います。内容は、テーマ(新規性、独創性、有用性)、実装(完成度、難易度)、発表(資料、プレゼン)の観点から、メンター陣で構成する審査委員により評価され、その結果、1位から6位までに入賞したチームは、上位から順に好みの副賞を選択して受け取ることができました。
ミニプロコンの詳細はコンテスト報告からご覧ください。
ミニプロコン
1位 curlおじさん(さくらインターネット株式会社) ベアメタル/KVM/コンテナ環境の統合運用ツールの構築
2位 RAY(神戸情報大学院大学) 持ち運びできるクラウドラズパイバッグ
3位 Seed(KBC) サイバー演習環境の自動構築
4位 kstm(信州大学) ゼロタッチプロビジョニング
5位 FUN-SDN(はこだて未来大学) SDNを用いた医療情報共有ネットワークシステムの検討
6位 334(琉球大学) 非接触型ICチップによるホームネットワークの認証&制御
ミニプロコンに続いて設けられた協賛セッションでは、さくらインターネット様とNTTコムエンジニアリング様からお話をいただきました。 協賛企業の担当者が会場を訪れて、会社紹介や業務内容を直々に語るこの時間は、若い参加者たちがその会社のことを知るよい機会であり、エンジニアを目指す若者たちは強く興味を惹かれている様子でした。
交流会と言う名の表彰式および夕食で多くの人と交流して貴重な情報を得た参加者たちは、再び会場に戻って、本合宿最初のチームミーティングに入りました。チームミーティングは、チームメンバとメンターによる議論の時間であり、合宿1日目のミニプロコン後に1回(1時間)、2日目に2回(計2時間)が予定されています。参加者はこの時間を使って、発表の点数やメンターコメントを参考にしたミニプロコンの振り返り、今後の方向性の見直し、スケジュールの見直し、face-to-faceによるメンターとの議論やアドバイスの吸収などを行います。 そしてそれを持ちかえり、テーマ自体や発表の内容をさらにブラッシュアップして、12月に行われるプログラムコンテストに向け、最後の仕上げに取りかかります。そのような重要な時間だけに、穏やかでリラックスした雰囲気でありながらも、真剣かつ突き詰めた議論がグループごとに進んでいました。
2日目のプログラムには、12月のプロコンを見据え、プレゼンテーションスキルを上げるための基礎講座が設けられました。 講師を務めたのは、メンターとして参加者を力強く支える、学校法人KBC学園 国際電子ビジネス専門学校 副校長の渕上真一氏です。渕上氏は「プレゼンは説得のコミュニケーションである」とその位置づけを明確にした上で、用いられる形式、ストーリ展開、人を引きつける伝え方、実践的なテクニック、準備すべきものなど、計画から実行に至るまでの各段階における貴重なノウハウを参加者に伝授しました。
一連の日程を終えた参加者たちは、大きなマイルストーンを乗り越えた自信を胸に、それぞれのホームグラウンドへと帰って行きました。つぎはいよいよ、この半年間の活動の集大成となるプログラムコンテストに挑みます。
















































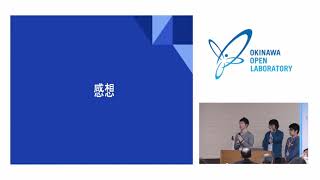









コメント