SDN/クラウド ミニプログラムコンテスト2016
- labs-admin
- 2016年8月26日
- 読了時間: 11分
2016年8月26日、国際電子ビジネス専門学校(沖縄県那覇市)において、一般社団法人沖縄オープンラボラトリ(以下OOL)が主催する「SDN/クラウドミニプログラムコンテスト2016」が開催されました。このコンテストは、SDN/クラウド技術を利用したシステムのアイディアを競い合うもので、12月第2週に開催される「SDN/クラウドプログラムコンテスト」の前哨戦に位置づけられています。
この日、コンテストに参加する各チームは、SDN/クラウド技術を用いたシステムやサービスのコンセプト、実現イメージ、アーキテクチャ、利用技術、開発スケジュール、デモなどを盛り込んだ発表を行い、その内容を、各方面の第一線で活躍する審査委員が、独創性、実現性、具体性、チャレンジなどの観点から審査しました。

各チームにとっては、受賞もさることながら、発表に対する審査委員らのアドバイスが大きな意味を持ちます。なぜなら、本選である12月の「SDN/クラウドプログラムコンテスト」に向けて、そのアドバイスがシステムや発表をブラッシュアップのための貴重なヒントになるからです。このレポートでは、同日の様子と結果について報告します。
- 自由かつ柔軟な発想でSDN/クラウドを活用するアイディアが次々と
この日、最初の発表を行ったのは、「九州濃厚ラボラトリ」チーム。テーマには「OpenStack間ネットワーク接続自動化」を掲げました。コンピュータの新しい利用スタイルである「クラウド」の分野では、複数のクラウドを連携させることによって、故障や災害に強いシステムの構築が可能になり、いま、その需要が増えています。このチームでは、OpenStackと呼ばれる広く普及するクラウドOSを対象として、各拠点のクラウド環境構築、そして、VPN接続を使った拠点間のクラウド環境の連携を自動化して、故障や災害に強いシステムの迅速な構築・提供と、それにまつわる人件費の削減を目指します。発表では、その実現に向けたコンセプトやアーキテクチャに加えて、OpenStack環境の手動構築に苦労していること、そして、既存のOpenStack環境同士を手動でVPN接続することには成功したことが報告され、その様子が紹介されました。発表後、会場からはOSインストールまで自動化するのかどうか、自動化の範囲はどこまでかを確認する質問などが出ました。
続いて登壇した「オープン北陸」は、「テストベッドを用いたツール検証環境自動構築化」をテーマとして発表を行いました。このテーマを選んだ理由には、(1)本社や支店ごとに存在する検証環境を集約してコストを削減する、(2)各部門で作成したツールを自ら検証できる環境を提供してツール開発にかかる時間を短縮する、(3)いつでも自由に検証に使える環境を提供して社員のスキル向上を図る、の3つがあるといいます。これを実現するため、典型的な構成を定義したテンプレートを画面から選ぶだけで、それに合致した仮想的なネットワーク環境とサーバ環境を自動構築し、それを使ってすぐにツール検証を始められる仕組みを構築します。なお、このテーマではOpenStack内の自動構築をおもに取り扱いますが、将来的にはOpenFlowなどSDN技術を組み合わせて、物理的な構成まで自動構成できるような拡張を検討しているということです。会場から出た「難しいとされるOpenStackのインストールはこなせそうか」との質問に、チームは「社内の若手の協力を得ながら進めたい」と回答をしました。
チーム「Weed」は、「ネットワークエンジニアへの近道 ~トラブルシューティングを用いて~」と題して発表を行いました。彼ら自身が学校で学んだ体験を基に、ネットワークへの関心の向上を図りながら、ネットワークに関する技術力が身につけられるよう、Webサービスとして提供するネットワーク故障エミュレータの実現を目指します。具体的な操作イメージは、難易度ごとに用意された問題をWeb画面で選択すると、その問題で想定するネットワークトポロジを表示するとともに、そのトポロジの仮想的なネットワークを自動構築して、それを使ってトラブルシューティングを行う、という流れになるということです。すでに、2つのMininetを2つのVyOSで接続する比較的シンプルなネットワークトポロジについては、その構築方法の確認を終えており、発表では、その様子を収録した動画も紹介されました。発表後の質疑応答では、「OpenStackにこだわり過ぎず、必要に応じてVMware ESXiのスナップショットなどを活用したほうが、円滑に進められるかもしれない」などのアドバイスが贈られました。
「クラウド技術を使って社会問題を解決したい」と語るのは「Mckee」チーム。彼らは「クラウドAPIを用いた社会問題へのアプローチ」と題して、いま話題のポケモンGOに関連する事件や事故が多発している事実にフォーカスを当てます。具体的には、スマホにばかり集中して周囲への注意を怠りがちなプレイヤ、そんなプレイヤとの事故を避けたい人、この両者をターゲットにした案内型マップアプリの開発に挑戦します。うちプレイヤに対しては、ポケストップやポケモンが出現しそうな場所を回る最短経路を計算したり、音声による案内を行ったりするということです。最終的には、Twitterのツイートに基づいたポケモン出現場所の推定、イベント情報に機械学習を適用しての交通量予測なども行う予定とのことでした。この発表では、Google Maps APIを用いたマップ表示や、Twitterからのツイート取得など、基礎的な実験を行う様子を収めた動画が紹介されました。会場からは、どうやってポケモンGO関連のツイートに絞り込むのかを聞く声があり、チームは、ポケモン名にハッシュタグを併用して検索することで対応する予定である旨を回答しました。
- 午後の発表では試作機を持ち込んでのデモンストレーションも!
午前中の発表が終わり、1時間ほどの昼休みをはさんで、午後の発表が始まりました。午後のトップバッターは「ごま苺」チーム。テーマには「研究に使用するクラウド環境を簡単に構築・管理しよう!!」を掲げ、インストールディスクをセットするだけの簡便な方法でクラウド基盤を自動構築可能な手段の実現、さらには、そうやって構築するクラウド基盤のなかに、簡単な操作でクラウド上に研究用の計算機リソースを用意できる仕組みの実現を目指します。発表の時点では、Linux自動インストールツールであるKickstartを用いて、KVMを使った環境の構築まで実現できているということです。この発表に対して会場からは「並列や分散アプリへの適用と使途に書いてあるが、KVMベースではデバグが困難なケースが生じるかもしれない」といった専門的見地からのアドバイスや、「資料の作り方や話し方がTPOに合っていない。他の人の発表を見るなどして、すこし変えた方がよい」との指摘などがありました。
「情報流出の低減を目的とした検疫システム」とのテーマを掲げ、セキュリティ分野へのSDN適用を目指す「SecLab」は、昨今急増している標的型攻撃の遂行段階を7段階に分けて、第4段階の「基盤構築」と第5段階の「内部侵入・調査」での対策が重要と分析しました。そして、この2段階における不正ソフトの異常な振舞いをネットワーク自身が検知・阻止すれば情報流出を防げると考え、SDNを用いてそれを実現するシステムの構築に挑んでいます。具体的には、クライアントコンピュータが行っている通信の内容(パケット)を評価して、そのクライアントの信頼度レベルを判定し、信頼度が低いクライアントの通信はSDNによりブロックすることで情報流出を防ぐということです。発表では、システムの動作概要、パケットの評価アルゴリズムについても、かなり踏み込んだ説明が行われ、システム方式の検討が進んでいる様子がうかがえました。会場からは「評価アルゴリズムの質を高めるために必要なテスト用データは入手できるのか」といった質問や、自ら定義する用語はその概念が十分理解されるよう丁寧に説明する、複雑な図ではどの部分について話しているかを明示する、といった点に気をつけるとよい、などのアドバイスが出ました。
京都産業大学でSDNの研究に取り組む3名が参加する「なんとなくメガネ」チームは、大学で取り組んでいること以外にも、もっと広くSDNのことを学びたいと考え、「リンク切断に対処可能なSDN Controllerを開発する」ことに挑戦します。このテーマでは、まずSTEP1で「OpenFlowスイッチが送出するPort Statusメッセージでリンク切断を検出し、それを契機にコントローラが代替経路を計算して、その結果に基づいて、代替経路へ迂回する設定をスイッチに投入する」ことを実現します。しかしこれには一定の時間がかかることから、STEP2では「あらかじめ予備経路を計算してOpenFlowスイッチに登録しておき、リンク切断が発生したら、Group tableのFast Failover機能により、OpenFlowスイッチが自律的に経路を切り替える」ことで、より迅速なリンク復旧を目指します。発表後半では、3台のコンピュータを3角形に接続し、宛先コンピュータがパケットを受信しているときにはビープ音が鳴っている状態で、通信に使用している1辺を人為的に切断し、一瞬、ビープ音が途切れるものの、すぐに鳴動を再開することで高速にリンク復旧する様子を見せるデモが行われました。会場からは「端末の他スイッチへの移動やブロードキャストセグメントの任意設定ができれば実用性は高い」「その発想力を生かして、年長者が思いもよらないような、ユニークなSDNの使い方を考えてみてほしい」といった評価やアドバイスが贈られました。
「Stone Hill」この日は「IoTにおけるセンサ・アクチュエータ間連携問題のSDNを用いた解決」と題して発表を行いました。このテーマでは、IoTデバイスの構成要素である、センサ、ロジック、アクチュエータをSDN AP(SDNスイッチを内蔵したWi-Fiアクセスポイント)に接続して、そのSDNスイッチを制御することで、各構成要素間のデータの振り向け先をWeb画面で自由に選べる仕組みを実現します。これが実現すると、センサ構成ファイルの書き換え、設定変更などをIoTデバイス個別に行う必要がなくなるため、大量のIoTデバイスが設置された際に、その管理の手間が大きく削減されます。発表の後半にはプロトタイプを用いたデモが行われ、センサ、ロジック、アクチュエータのSDN APへの自動接続、Web画面を用いての振り向け先設定、接続した不快度センサが実際に不快度の上昇を検出して警告音を発生する様子が示されました。この発表に対しては、彼らが最もチャレンジした部分をたずねる質問や、「実装やシステム構成図などを加えて、努力した部分をもっと見せる工夫をしたほうがよい」といったアドバイスが行われました。
発表のトリを務めたのは「まんぼう」チーム。テーマには「分散型クラウドシステムの構築」を掲げました。彼らは、避難所などを念頭に、インターネット上のサービスを利用するクライアントの近くにエッジサーバを配置して、インターネットの接続が不安定な状況でも、エッジサーバの働きで安定的にネットワークサービスを提供する仕組みの実現を目指します。この実現に向けての大きな課題は「通信が途切れている間に、エッジサーバと親サーバの両方のデータベースに加えられた変更を、いかに矛盾なく、相互に再反映するか」という点にあります。発表では、コンセプトやロードマップに加えて、この実現に向けた2つの方式(rsyncを利用、MySQLのfailover機能を利用)について試行錯誤する様子が報告されました。会場からは「MySQLのfailover機能は昔からあるものなので、P2Pなど新しい方式を加えたほうが面白い」といったアドバイスや、「通信復旧時にデータベースの整合性を取る主体はどれか」といった質問がなされました。
- いよいよ優秀チームの発表へ。喜びと充実感で笑顔の受賞者たち
9チームの発表がすべて終わり、別室で審査委員による審査が始まりました。審査時間はおおよそ40分が見込まれています。その間、発表を終えた各チームメンバは、発表を行った会場から、表彰式と懇親会が行われるサロンに移動して審査の終了を待ちます。
このミニプログラムコンテストでは優秀チームを4チーム選び、選ばれた各チームに、Cisco賞(副賞:Cisco社製スイッチ SF100D-08を1名1台)、NTTコム賞(副賞:Cloudn 半年利用権を1名1アカウント)、沖縄オープンラボラトリ賞(副賞:トップエンジニアとの交流、データセンタ見学など、希望する体験ができる体験券を1チーム1回)、特別賞(副賞:好きな技術書を1名1冊)のいずれかが贈られます。
いよいよ審査結果の発表が始まりました。参加者全員が見守るなか、名前が読み上げられたチームは、皆の前方に移動して、審査委員の講評を受け、副賞の目録を受け取ります。
Cisco賞を手にしたのは、リンク切断に対処するSDNコントローラの開発に取り組む「なんとなくメガネ」チームです。プレゼンターを務める審査委員の金海好彦氏(日本電気株式会社)は、「SDNとはいえ既存の技術の上に成り立っており、レイヤ2、3を学ぶことは大切だ。その際に、このスイッチを生かしてほしい」と講評を述べました。
NTTコム賞には、トラブルシューティングを学べるネットワーク故障エミュレータに挑戦する「Weed」チームが選ばれました。プレゼンターで審査委員の中島佳宏氏(日本電信電話株式会社 未来ねっと研究所)は、「このアプリを磨き上げて、クラウドで動く、様々な視点やシナリオを持ったトラブルシューティングシステムを実現してほしい」と自らの期待感を伝えました。
沖縄オープンラボラトリ賞を獲得したのは、SDNを使ってIoTデバイス管理の手間削減を目指す「Stone Hill」チームです。プレゼンターとして目録を授与した審査委員の吉田正之(OOL/株式会社アドックインターナショナル)は、「デモの完成度も高くよい内容だった。副賞を活用してIoTの最先端技術者と会い、さらにいいものを作ってほしい」と講評しました。
そして特別賞には選ばれたのは、クライアントの信頼度に基づき通信の可否を制御して情報流出の防止に挑む「SecLab」でした。プレゼンターで審査委員の田部英樹(OOL/NTTコミュニケーションズ株式会社)は、「たくさん学び考えたことが分かる発表だった。まだ調べなければならないことは多いだろうから、この副賞で必要な書籍を手に入れて、さらに勉強を」とエールを送りました。
優秀チームの表彰の後、全体の講評を述べた審査委員の藤田智成氏(日本電信電話株式会社 ソフトウェアイノベーションセンタ)は「12月の本番に向けて、今日はまだ道半ばだが、想像以上に勉強や実装が進んでおり審査委員も驚いた。この調子で引き続きがんばってほしい」と、各チームのここまでの努力をたたえ、今後の更なる進展に期待を寄せました。
*各チームの発表内容は参加者紹介ページよりご確認下さい。





































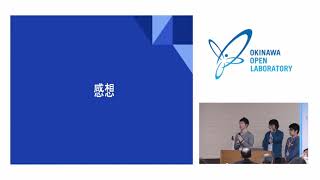









コメント